【2組の親子の体験談】親子の葛藤を経て見えてきたもの
登進研バックアップセミナー112 第1部抄録(2022年6月19日開催)
| ゲスト |
A男さん(21歳、大学4年生)+A男さんのお母さん(以下、A母)
B子さん(19歳、看護専門学校2年生)+B子さんのお母さん(以下、B母)
|
| 司 会 |
海野 千細(八王子市教育委員会学校教育部教育指導課心理相談員) |
| 助言者 |
小栗 貴弘(跡見学園女子大学心理学部教授)
荒井 裕司(登進研代表) |
※ゲストの方々の学年(年齢)は、セミナー開催時のものです。
学校は「罰を受ける場所」
| 海野 |
最初にゲストの方々から簡単な自己紹介をお願いします。
学校に行けなくなった時期やきっかけ、不登校だった期間、不登校になった当初の気持ち、家の中でどんなことをしていたかなども教えてください。
では、A男さんからお願いします。
|
| A男 |
こんにちは、A男です。21歳で、大学4年生です。当時の家族構成は、両親と4歳下の妹との4人家族です。
小学校5年生くらいから人間関係で嫌な思いをしていて、相手はじゃれているつもりかもしれないけど自分は嫌だったので、学校に行きたくなくなりました。小6から行けなくなり、中学校はほぼ丸々行っていません。
不登校になった当初はとにかく学校が嫌で、学校は「罰を受ける場所」みたいな印象をもっていました。学校でやることすべてが嫌だったので、それを無理やりやらされるのが、自分にとっては「罰」のように思えたんです。
学校に行かなくなってから、家ではインターネットで動画を見たり、いろんなサイトをめぐったりしていました。
|
| A母 |
A男の母です。最初のころはフルタイムで働いていましたが、息子が学校に行けなくなって、仕事どころじゃない感じで退職しました。
当初は、「学校に行かない」ことがどうしても受け入れられず、「行かせなくちゃ」という気持ちが強かったので、なんとかして行かせようとしました。
当時は「クラスメートにからかわれて嫌だ」ということも息子は言わなかったので、まったく知りませんでした。
小学5年の後半から行ったり行かなかったりという感じで、完全に行けなくなったのは卒業式の数カ月前くらい。でも、登校していた日もよく保健室に行っていたようです。それを知ったのが卒業式当日で、「A男さん、けっこう保健室に通ってましたよ」と言われて、本当に衝撃でした。
 中学校では、最初の1カ月半くらいは頑張って通っていたんですが、何か嫌なことがあったらしく、ある日、家に帰ってくるなりカバンを玄関にほうりだして、「もう行かない!」と言ったんです。
中学校では、最初の1カ月半くらいは頑張って通っていたんですが、何か嫌なことがあったらしく、ある日、家に帰ってくるなりカバンを玄関にほうりだして、「もう行かない!」と言ったんです。
それまでかなり無理をして行っていたんだと思います。あまりにもしんどかったらしく、そのころのことは本人はほとんど覚えていないようです。
|
| B子 |
B子です。19歳で、看護専門学校の2年生です。当時の家族構成は、母と私の母子家庭で、隣の家におばあちゃんが住んでいます。
中学を卒業してから大学付属の高校に入学し、1年の夏までは普通に楽しく通っていましたが、友だちとのトラブルで学校に行けなくなりました。
夏休みが明けると、長い休みのあとなのでもっと行きにくくなって単位を落としてしまい、「退学か留年か」の判断を迫られ、それなら転校しようと思って退学を選びました。
学校に行けなくなってからはずーっと部屋に閉じこもって、食事をまったくとらない日もあったり、母とも口をききませんでした。一日中、部屋は真っ暗。電気を消してカーテンも閉めて、ずっと布団の中にいて、みたいな感じでした。
当時は、友だちとのこともつらかったけど、おばちゃん(母の姉)が、中学のときからすごいスパルタで勉強を教えてくれて、おかげで高校もちょっといいところに入学できたのに行けなくなっちゃうなんて…。あんなに苦しい思いをして勉強したのになんで? という気持ちでした。
転校すればお金もかかるし、母に申し訳ないという思いもありました。
|
| B母 |
B子の母です。よろしくお願いします。
当時は、派遣職員として国民健康保険の窓口で働いていました。娘はそれまでは明るい感じで、1学期のころは友だちと毎週出かけたりして楽しく過ごしていたので、不登校になるとは思ってもいませんでした。
2学期のはじめに行かなくなったときもまさかという感じで、すぐに元気になるんじゃないかと思っていました。
 そのころは、毎日、「無理にでも行かなきゃダメだよ」と叱ったり、単位を落としそうになったときは「タクシーを呼ぶから、1時間でもいいから行ってきなさい」と無理やり行かせたりしました。
そのころは、毎日、「無理にでも行かなきゃダメだよ」と叱ったり、単位を落としそうになったときは「タクシーを呼ぶから、1時間でもいいから行ってきなさい」と無理やり行かせたりしました。
でも、行こうとするとじんましんが出たり、トイレに頻繁に行ったり、体調が悪くなったり、家を出てもすぐ戻ってきちゃったりしていましたね。
学校に行けなくなったとき、この子は「心の闇」をもっていたんだと感じました。とにかく、そのときの変わりようがすごかったんです。
髪の毛はボサボサで、人の目もまったく気にしない。何も怖くないというか、何かを捨てちゃった感じがして、ぜんぜん触れられない雰囲気でした。
私が仕事から帰っても家じゅう真っ暗で、一時的にスマホを取り上げたことがあるのですが、そのときは夜中にゴンゴン壁を叩くし、壁に穴は開けるし、「わーっ!!! 」と叫ぶ声はするしで、正直怖かったです。
そのころ親戚といろいろ話をしていたとき、いまでは笑い話ですが、この子は「多重人格」なんじゃないかと、そんな話が出るほど、あまりにも変わってしまったので、どう接していいのかわかりませんでした。
|
| 海野 |
B子さん、A男さん、少し落ち着いてきてからは、どんな生活を送っていましたか?
|
| B子 |
退学か留年か決めなければいけないリミットが高校1年の11月半ばで、その後、転校先の通信制高校が決まって12月に入学しました。でも、最初は「また同じことが起きたらどうしよう」と怖かったし、12月だともうクラスのみんなが仲よくなっていて、入り込めない感じでした。
だから、お昼の休み時間がつらくて午後から行ったり、最初はぜんぜん通えていませんでした。転校して2週間くらいで冬休みに入ってしまったので、タイミング的にもあまりよくなかったのかもしれません。
家では、ネット仲間とオンラインでおしゃべりするのが楽しみでした。人としゃべるのが好きだし、ネットだと気をつかわないで済むし、ハブるとかもないから、ネットで仲のいい人を作っておしゃべりして息抜きをしていました。
その後、2年生になってクラス替えがあってから少しずつ通えるようになりました。入学前からダンス部に入りたかったので、入学してすぐに入りましたが、最初のころは部活もぜんぜん行けなくて、ちゃんと活動しはじめたのは2年生になってからです。
|
| A男 |
僕の場合は昼夜逆転はなく、だいたい朝9時ごろには起きていました。不登校になって最初のころはずっと家にいたので、9時に起きて昼までネットを見て、昼食を食べてからまたネットを見て、という感じでした。
ネットを見ているといろいろ考えなくていいから、それで動画とかを見ていたんだと思います。中1の後半からは、2〜3日に1回くらい適応指導教室に通っていましたので、ずっと家にこもるような生活ではなかったです。
|
「受診するなら精神科でしょ」と娘に言われて
| 海野 |
お母さんに伺います。少し落ち着いてきてから、当初の対応と変わってきたことはありますか? 仕事に関する変化とか、相談機関に行ったとか…
|
| B母 |
私が仕事に行っている間、娘には何もしてあげられないし、帰宅すると、娘はネット仲間と話をしていることが多かったです。
このまま娘と接することも話をすることもできない状態が続くのかと思うと心配で、仕事をやめて家にいたほうがいいのかなとも考えましたが、母子家庭なので仕事をやめるわけにもいきません。それで上司に事情を話して遅刻や早退などに配慮してもらい、仕事を続ける環境を整えていきました。
医療機関については、最初はじんましんが出たりしたので皮膚科に連れて行ったりしましたが、ある日、本人から「受診するなら精神科でしょ」と言われて、精神科に行くようになりました。はじめは薬を処方してくれる病院に通っていましたが、途中からはカウンセリングを中心としたメンタルクリニックに通うようになりました。
|
「お母さんは仕事で忙しいから、おばあちゃんを呼んでください」
| A母 |
中1の後半くらいから、適応指導教室や通級指導教室に行くようになりました。適応指導教室は勉強勉強という雰囲気ではなく、まわりの人とのコミュニケーションを大事にする感じがしたので、いいなと思いましたし、本人も楽しいと感じるようになったのではないかと思います。
相談していたのは小学校のスクールカウンセラーの先生で、学校に行けなくなったとき、その先生のすすめでWISC(ウイスク)という検査を受け、「グレーゾーン」といわれました。そのときメンタルクリニックも紹介されて、中1から高1くらいまで2カ月に1回通っていました。その後、息子が高校1年になり、自分で動けるようになってきた段階でメンタルクリニックは卒業しました。
仕事については、最初に申し上げたとおり、息子が学校に行けなくなってから退職しました。中1のころは笑うこともまったくなくなって、大丈夫かなと不安になるくらい真っ暗な目をして、ほっといたらいなくなっちゃうんじゃないかと思うくらいの感じだったので、仕事に行ってる場合じゃないな、と。
退職を決めたのは、小6のときの経験があるからかもしれません。小6のとき、職業体験で河原に行って転んで頭を打ったことがあって、それで病院に行くとき、息子が担任の先生に「お母さんは仕事で忙しいから、おばあちゃんを呼んでください」と言ったらしいんです。そのころ私は契約社員になったばかりで、子どもは「お母さんが仕事をしているのは重要なことなんだ」「邪魔をしちゃいけない」と感じていたのかなと思います。
それ以降、よく頭が痛いといって学校を休むようになり、それで私が仕事に行っている間に何かあったら…という心配もあり、ここでいったん仕事をやめて様子を見ようと思いました。
|
| 海野 |
お母さんとしては、どんなことを考え、どんなことが不安でしたか?
近所や祖父母・親戚などへの対応、きょうだいへの影響などで大変だったことはありますか?
|
| A母 |
中1のときに「もう行かない!」と言われてから、本当に行きたくないんだとわかったので、家にいる時間を大切にしようと考えるようになりました。
メンタルクリニックで自己肯定感が低いといわれたので、家のことを手伝ってもらって「よくできたね」とほめたり、朝起きてきたら「起きれたね」と言うようにして、小さなことの積み重ねですが、一つひとつの行動を認めてあげるように心がけました。
適応指導教室に行きはじめたときも、「適応指導教室だって学校なんだから、学校に行っているのと同じだよ」と話していたので、息子の中に「学校に行ってない」という不安や劣等感のようなものはあまりなかったんじゃないかと思います。
親戚への対応については、自分の母には「学校に行ってないんだよ」と正直に話しましたし、学校に行ってないからといって外に出ちゃいけないわけではないから、息子が興味のありそうな体験教室に連れ出したり、親戚と一緒に出かけたり、普通に生活していました。息子のことで親戚から私が責められることはなく、逆に協力してもらった感じです。
夫は、当初、「学校に行けない」ということが理解できないようで、私と一緒に無理やり登校させようとしましたが、その後は息子と2人で自分もやったことのない釣りをしたり、一緒に過ごす時間を大事にしようとしていました。
私は不登校のセミナーなどにどんどん行って、「ああだった、こうだった」と家族にぜんぶ話していましたし、担任の先生が「男の子は、お母さんよりお父さんの力が必要」と言っていたことを伝えて、「子育てはひとりでやるんじゃないから」「あなたにも責任があるから」みたいな感じで、夫も一緒にやってもらうように声をかけていました。
きょうだいの対応については、妹が「にいにが学校に行かないのに、なんで私だけ行かなきゃいけないの?」とすごく言っていました。そのときは、「お兄ちゃんは、お兄ちゃんだから」と答えたり、妹に「学校、楽しい?」と聞くと、楽しいと答えるので、「じゃあ、行かない理由ないよね?」と言ってみたり(笑)。「お兄ちゃんは学校で嫌なことがあって、行きたくても行けない状況なんだよ」とか、その場その場で説明していました。
|
壁ぎわに忍者みたいに張りついている娘を見て…
| B母 |
前の高校をやめたとき、娘と一緒に私物を取りに学校に行ったんですが、放課後でもう生徒は誰もいないのに、人が怖くてまっすぐ行けないんです。遠回りをしながら、壁ぎわに忍者みたいに張りついて進むような感じで、そのとき、ああ、本当にダメなんだなと実感しました。
うちは祖母がすごく心配して、「病院に連れていったほうがいいんじゃないか」とかいろいろ言ってきましたが、自分でも気持ちの整理がつかない状態でしたので、それを受けとめるのが大変でした。
祖母は隣に住んでいるのですが、いつもこの子がどうしているか気になって、わが家のほうに顔を向けてばかりいるらしく、体が固まっちゃって肩を傷めてしまうくらい心配していました。
私の姉とは、一時期この子が「会いたくない」という感じになりました。
姉は、この子がネット仲間とオンラインでおしゃべりしているのをなぜか知っていて、「スマホを取り上げたほうがいい」「スマホ依存症を治す病院があるから、そこに入院させたほうがいい」「そうしないと大変なことになる」とか極端なことを言うタイプなので、私は姉と娘の板挟みになって大変でした。
子どもが不登校になると、父親が「お前の育て方が悪いからだ」と母親を責めるという話がありますが、うちの場合は、姉が父親のようで、「そんなだから、こんなことになるんだ」とかすごくいろいろ言われました。
|
| 海野 |
子どものことで「ここが理解できない」と思ったことはありますか?
|
| B母 |
私は、学校に行かない状態が続いたらどうなるんだろうと不安でたまらないのに、娘にはそういう危機感がないような気がしました。
印象に残っているのは、不登校中に遠足があって、娘は前日まで参加するかしないか葛藤していたのに、結局、参加して楽しんできちゃったり…。
学校の単位を落としそうになっていたころ、そんなせっぱつまった時期に調理実習に参加して、自分でグループを仕切ってチャーハンを作って、けっこう楽しくやっていたり…。
学校をやめるかどうかの瀬戸際で、かなり深刻な状況なのに、何を考えているんだろうと理解できませんでした。多重人格なんじゃないかと(笑)。
|
| B子 |
危機感がないわけじゃなくて、高校をやめたら高卒資格も取れないのでヤバいなとは思っていたんですが、学校に行きたくない気持ちのほうが強かった。
とにかく学校に行きたくないので、単位を落としそうな科目の授業がある日は遅刻して出席し、その授業が終わったら早退するという、ギリギリの線でやっていました。
 調理実習や校外学習は、すでに学校をやめるつもりでいたこともあり、事前にもらった案内で仲のいい子たちと一緒のグループだとわかったので、最後の思い出づくりのつもりで参加しました。
調理実習や校外学習は、すでに学校をやめるつもりでいたこともあり、事前にもらった案内で仲のいい子たちと一緒のグループだとわかったので、最後の思い出づくりのつもりで参加しました。
危機感がないように見えたかもしれないけど、自分なりにいろいろ考えていました。決して多重人格ではありません(笑)。
|
| 海野 |
A男さんのお母さんは、息子さんのことで「理解できない」と感じることはありましたか?
|
| A母 |
息子はいろんなことを考えていたと思いますが、言葉で伝えるのが苦手なこともあり、なんでも心の中にしまいこんでしまうので、私が「どう思っているの?」と聞くと、黙り込んでしまうことが多かったように思います。
彼がどう伝えようか考えている最中に、私がせっかちで答えを急がせるので、嫌気がさして黙ってしまうんだと思います。それで、何を考えているかわからずじまいになってしまう。そういうすれ違いがあったと思います。
いま考えると言葉で追いつめていたわけで、本人はつらかったと思います。
|
| A男 |
母がすぐに「どうなの?」と聞いてくるのが嫌だったんだと思います。考えてから言葉にするまで、けっこう時間がかかるほうなので、その途中で「どうなの?」と問い詰められると、「自分の話を聞く気がないんだな。話すまでじっくり待ってくれないんだな」と思って、言わなかったんだと思います。
|
あわてて退学届を出さないで!
| 海野 |
荒井先生、先ほどB子さんから転校の話が出ましたが、ここで「転校するときの注意点」について簡単にお話ししていただけますか。
|
| 荒井 |
B子さんのように、進級に必要な単位が取得できないために転校しようかと考える場合には、すぐに退学届を出さないことがポイントです。
転校というのは学校と学校のあいだに橋をかけようとすることですが、次の学校が決まらないうちにいまの学校をやめてしまうと、その橋がかからなくなってしまうからです。
たとえば、高1の2学期に「もうこの学校に通いたくない」と思って退学届を出してしまうと「中退」という形になり、その後、他の高校に転校(編入)する場合には、中退時の学年(高1)を、もう一度、最初(4月)からやり直さなければなりません。橋がかからなくなるとはそういう意味です。
対して、転校先の高校を決め、諸手続きを済ませてから転校(転入)する場合は、新しい学校でも高1の2学期から再スタートすることができます。
なお、私が学園長を務める学校(通学型の通信制高校)でも多くの転入生を受け入れており、在校生に占める転入生の割合は1年生で20%にのぼります。つまり、それだけいまの学校が合わない子どもが多いということだと思います。だからこそ、自分に合う新しい教育環境を求めて転校しようと思ったら、「あわててやめない」「すぐに退学届を出さない」ことが大事だということを覚えておいてください。
|
| 海野 |
親として、子どもへの対応や声かけで気をつけていたことはありますか?
「夕ごはんは一緒に食べる」とか家庭内で何か決め事はありましたか?
|
| A母 |
私は子どもが答えようとするのをじっくり待てない性分なので、子どもが答えそうな選択肢を事前にいくつか用意して、「どれがいちばん近い?」という聞き方をして、答えが出るまでできるだけ待つように心がけました。
待ちすぎて、何を質問したのか忘れてしまうこともありましたが(笑)、そういう対応をいろんな場面でするように気をつけていました。
 家庭内でのルールはとくに決めませんでしたが、ゲームの時間だけは2時間と制限しました。適応指導教室に行かない日はずっとやり続けることが多かったので、「これだけは守ろうね」と言いました。
家庭内でのルールはとくに決めませんでしたが、ゲームの時間だけは2時間と制限しました。適応指導教室に行かない日はずっとやり続けることが多かったので、「これだけは守ろうね」と言いました。
守らないとゲームを没収することもありましたが、食事だけはリビングに出てきてみんなと一緒に食べて、また部屋に戻るという感じでした。
|
| B母 |
私は、なるべくこれまでと変わらずに接していこうと思っていました。
「学校に行ってないのに外に連れ出すのはどうなの?」と姉に言われましたが、休日などに本人が行く気があれば、気分転換を兼ねて外に誘いました。
娘は動物好きなので、私の友人の実家で何百羽もインコを飼っているお宅があって、そこに遊びに行かせてもらったり、なるべく外に連れ出すようにしていました。また、親としての不安や葛藤をできるだけ本人にぶつけないように心がけていました。
|
スマホを取り上げられるのは、親友を奪われるのと同じ
| 海野 |
A男さん、B子さん、親の対応で嫌だったことやうれしかったことがあれば教えてください。
|
| A男 |
いちばん嫌だったのは無理やり学校に連れていかれることでしたが、そういう対応がなくなってからはある程度自由にしてくれたのでうれしかったです。
強いてもうひとつあげれば、2時間という約束を守らないとゲームを取り上げられるのも嫌でしたね。2時間はすごい短いなと思っていました。それと、両親がおいしい食事を作ってくれることもうれしかった。とくにガリバタチキンなど肉系の料理が好きでした。
|
| A母 |
ゲームについては、2時間という制限ではなく、夜9時までという制限だったかもしれません。それは昼夜逆転を避けたいと思ったからで、そのため起床時間や就寝時間もわりと気にしていました。
一時は無理やり起こしたこともありますが、友だちと約束があると朝4時半でもちゃんと起きるので、やりたいことがあれば起きれるんだ、すごいなと思っていました。逆に考えると、朝起きてこないのはやっぱり学校に行きたくなかったんだなと思いました。
料理については、主人が元コックで休みの日とかは作ってくれます。主人が作ると肉料理メインでボリュームたっぷり、私が作るときは野菜メインです。
あの、誤解のないように申し上げますと、料理は基本、私が作っているんですよ(笑)。子どもが小さいときから親しんできたのは、私の味だと思います。でも、男の子は大きくなると肉食怪獣ですから、肉さえ焼いていれば問題なしみたいな感じなので、主人の肉料理がウケたんだと思います。
|
| A母 |
親の対応で嫌だったのは私も同じで、「学校に行きなさい」とうるさく言われることでした。
それと先ほどネットの友だちとの交流について話しましたが、ネットについてはマイナスイメージを抱いている方が多いと思います。でも、私が動き出そうと思ったのは、ネットの友だちとの交流があったからです。
私のなかには、不登校になったことについて「恥ずかしい」という思いがありましたが、ネットの友だちにも同じ経験をした子がたくさんいることがわかって、不登校に偏見をもっている人も少なく、自分だけではないんだという安心感もありました。
 だから私にとって、そうした交流手段であるスマホを取り上げられることは親友を奪われることと同じだと思っていました。
だから私にとって、そうした交流手段であるスマホを取り上げられることは親友を奪われることと同じだと思っていました。
うれしかったのは、母子家庭で仕事も忙しいのに、転校するときに母がいろいろ学校を探してくれたことです。気分転換のために外出につきあってくれたこともうれしかったです。
|
お母さんの電話が私の部屋につつ抜け(笑)
| 海野 |
お母さんが、気分転換やストレス解消のためにしていたことはありますか?
|
| B母 |
ストレスがたまると子どもに当たってしまうので、職場の先輩や知り合いのお母さんなど信頼できる人に話を聞いてもらって、不安や怒りを吐き出すようにしていました。
ひとり親なので相談できる家族がいませんから、気持ちを共有してくれる人がいるだけで精神的にとてもラクになりました。
子どもの言動をまともに受けとめると、どうしても感情的になってしまうという話をしたら、「イラッとしたときは心を凍らせるんだよ」というアドバイスをもらいました。それを実践したらうまく気持ちを切り換えられるようになって、あまりストレスを感じなくなりました。とてもありがたかったです。
|
| B子 |
職場にも相談できる人がいたことは知りませんでしたが、母が知り合いのお母さんに電話で相談しているとき、その話がぜんぶ2階にいる私に聞こえてきたことがあって(笑)。それを聞いて、私の不登校のことで私と同じように悩んでくれているんだな、自分もなんとかしなきゃいけないなと思いました。
|
| A母 |
子どもが学校に行っていない姿を目にすると落ち込んでしまうので、できるだけ自分の時間をつくるようにしていました。体験教室に行ったり、友人や同じ不登校の子をもつお母さんと会って話をしたり、体を動かすと気持ちに余裕ができるので子どもを優しい目で見ることができました。
近くの川沿いにジョギングコースがあるので、日常的にランニングをしていました。運動のモチベーションを維持するために目標を立て、市民マラソン大会にも出場するようになりました。
不登校にこだわると視野が狭くなりがちですが、走りながら景色を眺めたり自然にふれることで、広い視野で物事を考えられるようになりました。
マラソン大会に出場すると達成感も得られるし、自分をほめてあげることもできるようになり、息子に対してもほめてあげられるようになりました。
 もうひとつ、ランニングをするなかで感じたことがあります。
もうひとつ、ランニングをするなかで感じたことがあります。
私は膝に持病があり、走りたくても一歩も走れないことがあるんです。そのとき、子どもが学校に行きたいと思っても体が動かないというのはこういうことなのかなと、身をもって感じたことがありました。これはしんどいよね、と。
|
| 海野 |
不登校であることを自分ではどう思っていましたか?
また、親は不登校である自分をどう思っていると感じていましたか?
|
| A男 |
学校に行かないことがそんなにダメなことなのかなと疑問に思い、学校に行かなきゃ学べないことがそんなにあるのかなというひねくれた見方をしていました。学校に行かなくても学ぶ意欲さえあれば、いくらでも学ぶチャンスや環境はあるんじゃないかと思っていた時期もあります。
中学校のときは適応指導教室に通っていて、完全に不登校状態だったのは小6から中1のころですが、精神的に幼かったこともあり、親が不登校の自分をどう思っているかについてはあまり考えなかったですね。
|
| B子 |
不登校になったことで「恥ずかしい」とか「普通じゃないな」という感じはもっていたし、おばさんに勉強のサポートをしてもらって、せっかくいい高校に入れたのに、行けなくなるなんて自分は最低だなと思っていました。一方で、高校をやめたら「負け」だなというプレッシャーも感じていました。
同級生にも同じようなことを言われましたが、まさか自分が不登校になるなんて思ってもみなかったので、どうしたらいいかまったくわからない状態でした。母も私と同じように「まさかこの子が不登校になるなんて」と思っていたはずで、ガッカリしていたと思います。
|
LINEで「最低な親だな」と言われて
| 海野 |
親として不登校の子どもを受け入れることはなかなか難しいと思いますが、そのへんのご自身の葛藤についてお聞かせください。
|
| A母 |
とにかくどうすればいいかわからないので、情報を集めるためにセミナーに参加したり、不登校のお子さんの保護者と話をするうちに、知識や情報がないから不安になるんだと思うようになりました。
子どもへの対応もいろんな考え方があることを知り、進路情報もいろいろあることがわかってきて、少しずつ不安がなくなっていきました。
そのなかで子どもへの対応の仕方も、実際に試してみて、このやり方は息子には合わないとか、こっちのほうが受け入れやすいかもとか、試行錯誤をしながらやってきたような感じがします。
 そのころはまだ「学校に行くことがすべて」という考え方でしたが、しだいに最終目標は学校に行かせることではなく、「本人の自立」だと思うようになっていきました。
そのころはまだ「学校に行くことがすべて」という考え方でしたが、しだいに最終目標は学校に行かせることではなく、「本人の自立」だと思うようになっていきました。
それで家事の手伝いをやってもらううちに、料理やアイロンがけなどもできるようになって、適応指導教室の調理実習でも「A男さんは卵焼きがとても上手」という評価をもらって自信につながったようです。
そうして人に認められ、頼られることで、自分でやらなければいけないという意識が芽生えたのではないでしょうか。
|
| B母 |
当初は、まさかこの子が不登校になるなんて、という感じで、なかなか受け入れることができませんでした。
実は、娘が単位を落として学校をやめるしかないという状況になったころ、ちょうど2人で出かけようとしたそのとき、娘と同じ高校を受験しようとしている子のお母さんからメールが来て、高校の状況について聞かれたんです。
そのメールを見て、思わず私は「自分の娘が学校をやめようとしてるのに、学校の説明なんかできるわけないじゃない」と言ってしまい、怒った娘はひとりでどこかへ行ってしまいました。その後、娘からのLINEで「最低な親だな」という、私をボロクソに非難した長文のメッセージが届きました。
そのことがあってから、私の抱えている葛藤は、私自身が世間体を気にしすぎていることから生まれるんだと気づいて、そのころ若者の自殺が増えているという報道もあり、大切なのは「この子が楽しく元気に生きていてくれること」なんじゃないかと気持ちを切り換えることができました。
いよいよ高校をやめる段階になったとき、本人はつらい経験からやっと解放されると思ってすごく喜んでいて、一方、私はせっかく猛勉強して入学した高校なので未練があって泣けてきてなかなかあきらめがつかなかったんですが、このLINEのことがきっかけで変わることができたと思っています。
|
| 海野 |
お子さんが動き出す兆しを感じたことはありますか?
いつごろ、どんなことでそれを感じましたか?
|
| B母 |
いまの高校をやめることが決まったその日に、娘が「看護師を目指す」と言って、将来やりたいことを私にプレゼンしてくれたんです。
それは先に進もうという意思のあらわれで、本来は喜ぶべきことかもしれませんが、退学した日にいきなり将来の話をされてもついていけず、「こんな日になんなの! 私がどれだけショックかわかってるの?!」と怒ってしまいました。
そのせいで険悪ムードになり、あ〜あ、また失敗しちゃったと思ったんですが、学校に行けなくても将来のことは考えていたんだと、ちょっとうれしかったです。
それ以外にも、これまで娘はメンタルクリニックでの治療に積極的になれず、クリニックに行く途中で帰ってしまったり、先生から出された課題もやらなかったりしたんですが、ある日、診察室で先生と笑いながら話をしているのが聞こえてきてびっくりしました。
先生が提案する目標にも積極的な姿勢を見せるようになり、自宅でも洗濯物を取り込んでくれたり、夕飯を作ってくれたこともあって、ちょっと動きが出てきたなという印象がありました。
もうひとつ、2人で外食をしているとき、肉料理を食べながら「おいしい」と言ったんです。それまでは外食に連れ出しても「食べたくない」と言うことが多く、無理やり食べさせる感じでしたが、「おいしいって幸せなんだね」と言ってくれたときは、おいしいものをおいしいと感じる感覚を取り戻してくれたんだと、本当にうれしかった。
|
| A母 |
適応指導教室に行くとき、最初のころは送っていったのですが、そのうち途中で「もうここで帰っていいよ」と言うようになり、最終的には玄関を出たら、「ひとりで行くからいいよ」になりました。そんな姿を見るうち、「ああ、自分で歩き出そうとしているんだな」と感じて、じゃあ任せてみようと思いました。
|
友だちに会う楽しみができたのが大きなきっかけ
| 海野 |
動き出そうとするきっかけになったことはありますか?
そのとき、親はどんなサポートをしてあげたらいいですか?
|
| B子 |
高校をやめたことで、それまで積み上げてきたものがゼロになっちゃった感じで、どうしたらいいかわからず、真剣にこれからのことを考えました。
まず不登校で乱れた生活習慣を整えて、家事も少しは手伝って、もともと保育士とかペット系の仕事に進みたかったので、なんとか高校卒業資格を取得してから専門学校に進学しようと思っていました。
 看護師になりたいと母に伝えたのは、ペットや人の世話をするのが好きなのと、人の役に立ちたいという気持ちがあったからです。
看護師になりたいと母に伝えたのは、ペットや人の世話をするのが好きなのと、人の役に立ちたいという気持ちがあったからです。
最初は不登校のときにお世話になった保健室の先生みたいになりたいと思い、そのために看護師の資格を取ろうと考えて、母に相談したという経緯があります。
親にしてほしいサポートは、子どもは親が思っている以上にいろいろ考えて行動しているので、その子がやろうとしていることが絶対無理だと思っても、しばらくは見守ってあげてほしいと思います。
不登校のとき、私は一日中ネットで延々と話をしているような生活をしていましたが、ある日突然、このままではダメだと思って動き出しました。そういう瞬間が誰にもあると思うので、友だちとの交流についても、あまり縛らないで見守ってほしいです。
|
| A男 |
僕の場合は、適応指導教室で2〜3人の友だちができて、友だちに会う楽しみができたことが動き出す大きなきっかけになりました。
動き出そうとするときに親にしてほしいサポートは、子どもが困ったときに助けを求めるのは親しかいないので、そのときにすぐに対応できるように準備をしておくだけでいいんじゃないかと思います。
ただ、それなりの親子関係ができていないと子どもが助けを求めるのは難しいと思うので、「学校に行く/行かない」以外の会話、夕食の味つけがどうだとか、ささいな日常会話を積み重ねていって話しやすい雰囲気をつくり、困ったときに子どもが助けを求められる環境を整えてあげてほしいと思います。
|
「見守るは一日にして成らず」
| 海野 |
小栗先生、子どもが動き出そうとしたとき、親はどんなことに気をつけて対応すればいいのかアドバイスをお願いします。
|
| 小栗 |
いま、B子さんもA男さんも、親にしてほしい対応として同様のことを話してくれました。
B子さんさんは、大人が考えている以上に子どもはいろいろ考えているから見守っていてほしい、A男さんは子どもが助けを求めたときに動けるように準備をしておいてほしいということでした。
つまり、まったくかかわらないでほしいというのではなく、つかず離れずの距離で見守っていてほしいという、共通の願いが2人から出されたことがとても印象的でした。
見守るというのは、子どもが失敗しないように先回りして手助けすることではありません。
たとえば、不登校状態にある子が、やりたいことが見つかって動き出そうとするとき、親から見たら「それはちょっと無理があるな」ということでも、無下に否定しないことが大切です。
それが子どもの原動力になるかもしれないし、それに向かって進もうとしている子どもにストップをかけるより、応援してあげる方向でかかわることができたらいいなと思います。
難しいのは応援するときの距離感ですが、子どもの前に出てひっぱるのではなく、先回りしてやめさせるのでもなく、「見守る」姿勢が重要です。頑張りすぎる傾向のある子には、本人の望む方向性を保ちながらも、頑張りすぎてリバウンドが起きないように少しブレーキを踏んであげるといいと思います。
「見守るは一日にして成らず」で、そう簡単にできることではありませんが、基本的には信頼関係の上に成り立つものですから、まずA男さんが話してくれたように、親子のふだんの会話、食事をしながらとかテレビを見ながらとか、「おはよう」「おやすみ」のあいさつとか、そういうなんていうことのない会話を大切にして、コミュニケーションを図っていくことが重要です。
|
高校選びの決め手は「ここなら通えるんじゃないか」という雰囲気
| 海野 |
A男さんの場合は進学、B子さんの場合は転入ですが、その学校を選んだときの決め手になったのはどんなことですか?
|
| A男 |
進学についてはギリギリまで考えていなかったんですが、環境が変わることで、新しい友だちができるかどうかは不安でした。
高校を3校くらい見学して、「ここなら通えるんじゃないか」という雰囲気を大事にして決めました。雰囲気というのは、直感で「ここなら大丈夫かな」と判断したことなので、具体的には説明できませんが。
その学校は「茶髪禁止」「ピアス禁止」など厳しめの校則があったんですが、僕は髪を染めようとか思ってないし、ピアスにも興味がなかったので気になりませんでした。
|
| B子 |
将来の夢を実現するには、まず高校卒業資格を取得しなければならないので通信制高校に行こうと思っていました。おばさんが通信制のパンフレットをいくつか取り寄せてくれて、そこに見学に行きました。
私も雰囲気で選んだほうですが、選んだ高校は、先生方が初対面なのにとてもフレンドリーに接してくれたり、話しかけてくれたので安心できました。
正直言うと、通信制高校だから金髪やピアスは当たり前、ヤバい子もたくさんいるだろうし怖いなというイメージがありましたが、実際に見学に来てみたら、校則もあって真面目な生徒が多い感じで、ちゃんと学校行事もあり、毎日通学したい人は通えるシステムになっているので、そこに決めました。
|
| 海野 |
親子で何校か学校見学や説明会に行ったと思いますが、進路選びで重要視したのは、どんなことですか?
|
| A母 |
事前に学校の情報はかなり集めていました。通学時間や乗換駅の状況も確認し、息子に合いそうな学校をいくつか選択しておいて、息子が実際に見てみたいと言った学校に連れて行きました。
最終的には、その学校の先生と面談しているときの本人の楽しそうな表情を見て決めました。息子が希望していた「声優・タレントコース」の体験授業もあって、それも「受けてみる」と言い、自分から進んでいろいろやっていたので、ここなら学校生活を楽しめるかなと思いました。
 親としては、小中学校のころのように学校が「嫌な場所」というイメージで終わるのではなく、楽しめる場所であってほしいと思っていました。
親としては、小中学校のころのように学校が「嫌な場所」というイメージで終わるのではなく、楽しめる場所であってほしいと思っていました。
それと、高校卒業後に就職する可能性もあるので、そのときにルールを守るなど基本的なことが重要になってくるので、通信制高校でも、ある程度決まり事がきちんとしている学校のほうがいいかなと思っていました。
|
| B母 |
進路選択で重視したのは、なによりも本人の気持ちです。
最初に娘と一緒に学校見学に行ったのは、事前に私が下見をして「ここならいいかな」と感じた高校でした。
見学当日、娘はその学校の生徒たちが登校する風景を遠くから見ていたんですがイマイチな反応で、帰りに印象を聞いたら泣き出して、「もう誰とも接したくない」と黙り込んでしまいました。
次にもうひとつ候補になっていた通信制高校があって、そこに見学に行きました。その学校には「ペット・アニマルコース」があって、動物好きな娘はパンフレットを見てピンと来たようです。
娘は、学校見学などで先生方と面談しても、ずーっとニコニコしているだけで、その場で自分の意見や感想を言えないことが多いんです。ニコニコ笑ってうなずいて話を聞いていたから、「あの学校、気に入ったの?」と聞くと、「嫌だった」ということもけっこうありました。
そこで、その通信制高校の面談に行くとき、事前に「嫌だったら制服のネクタイを手で触る」というサインを決めておいたんです。すると、そのサインが出なかっただけでなく、娘が興味のあったダンス部の顧問の先生が練習風景を見学させてくれ、先輩たちもみんな感じがよかったと、心からのニコニコ顔で戻ってきました。
振り返ってみても、やはり本人の気持ちを優先してよかったと思います。
|
| 海野 |
先ほど、茶髪禁止やピアス禁止など校則の話題が出ましたが、荒井先生の学校ではどんな状況なのか教えてください。
|
| 荒井 |
私の学校(通信制高校)はサポート校から出発していますので、歴史は長いほうだと思いますが、最初は制服はありませんでした。
ところがその後、中学時代に不登校だった子どもたちは、学生らしさの象徴である「制服」に憧れを抱いていて、高校生になったら「制服を着て学校に通いたい」と思っている子が圧倒的に多いことがわかりました。そこで早速、制服検討委員会を立ち上げ、制服のデザイン等を決定したという経緯があります。
茶髪やピアスは自己表現のひとつだと思いますが、私たちの学校に入学してくる子どもたちの多くは、人間関係で傷ついたり、いじめられた経験があり、茶髪やピアスをした生徒を見ると反射的に怖いと感じてしまうのです。そんな子どもたちに安心して楽しい高校生活を送ってほしいという思いから、わが校ではあえて茶髪やピアスは禁止しています。
制服や校則については、その子の考え方に合った学校、その子らしさを認めてもらえる学校なのかどうかを、説明会や学校見学を通して確認することが大切です。
|
「無理にニコニコする必要はないからね」
| 海野 |
転校した(A男さんの場合は入学した)高校での生活はどうでしたか?
|
| B子 |
通信制高校は家庭学習が中心なのかと思っていたら、毎日通学できて、いろんな行事も部活もあって、友だちもたくさんできて、まるで「ザ・高校生活」みたいな時間を過ごせるなんて驚きでした。
先生たちが、不登校だった私たちの気持ちをよく理解してくれているのもよかったです。先ほど母が私について、いつもニコニコしているけど本当は何を考えているかわからないという話をしていましたが、ある先生が「無理にニコニコする必要はないからね」と言ってくれたときは本当にうれしかった。
私にとって高校生活=ダンス部という感じだったので、授業には出ないのに放課後の部活だけは参加するという日がかなりありました。
ダンス部の卒業公演ではミュージカル『美女と野獣』を上演し、私が主役を務めました。配役は部内のオーディションで決めるのですが、人前で何かを表現したり話をするのが苦手なので、2年生のときはオーディションをすっぽかして帰ってしまったくらいです。
 そんな自分が1年間で成長できてオーディションも受けて、主役を演じることになるなんて自分でも信じられません。
そんな自分が1年間で成長できてオーディションも受けて、主役を演じることになるなんて自分でも信じられません。
ずっと人前で話すのが苦手でしたが、ダンス部で大勢の観客の前で表現することや、できなくてもとりあえずやってみようと挑戦する機会が増え、性格も少しずつ変わってきた感じがします。
自分はダンス部でいちばん変われたと思っていて、前の学校をやめて本当によかったというか、私に嫌がらせしてきた子に対しても、逆に、「ありがとう」って思えるくらいです。
|
| A男 |
1年生のころは、中学校での嫌な経験もあるので、あまり積極的に活動したわけではありませんが、友だちは5人くらいできました。不登校という同じ経験があるので話しやすかったこともあります。
2年生から少しはっちゃけはじめて、文化祭で部活発表のときに『美女と野獣』という演劇で王子の扮装をしてステージに立ったりしました。昼休みに学校の前にできた店からピザを買ってきて教室で食べたり、少しずつ行動が大胆になってきて、3年生になって完全に振り切った感じです。
|
| 海野 |
新しい高校に転校してから(A男さんの場合は入学してから)、お子さんに何か変化はありましたか?
|
| B母 |
いま、娘が「前の学校をやめて本当によかった」と言っていましたが、通信制高校での生活は最初からスムーズに進んだわけではなく、いろいろな壁がありました。
ダンス部で先輩とペアを組んで、相手の演技のダメな部分を指摘し合ったり、相手の演技をマネる練習が苦手で、熱を出したり、通えなくなったこともあります。そんなことのくりかえしで大丈夫なのかなと思うときもありました。
1年生の12月からダンス部で活動を始めましたが、当時の3年生の卒業公演は2日間の宿泊合宿をやってから当日に臨むのです。でも、娘は「今回は見学にするから合宿にも行かない」と言うので、また苦手意識が出てきたのかなと思っていました。
ところが、頑張って合宿に参加してみたら、苦手な先輩とも打ち解け、怖いと思っていた指導の先生も実は優しい人だったとわかり、そうやって自分の中のハードルがひとつひとつ解消されて、最後に卒業公演にも参加できたことが大きかったのかもしれません。
最後の卒業公演で、同じ学年の友だちと主役の座をかけてオーディションで競うことになったとき、以前なら娘のほうが辞退したはずなんです。でも、辞退しなかった。やりたいことのために友だちと競い、合格した。大きな成長だったと思います。その友だちともいい関係を築けているようで、それが大きな転機になったのかもしれません。
|
| A母 |
1年生のころは、新しい環境に慣れるのが大変だったようで、疲れきって帰ってきたり、休む日も多かったと思います。
そのうち友だちができたことで少しずつ慣れてきたのか、文化祭のアート部の発表では、女子のなかに男子がひとりという状況でしたが、わりと頼られる存在だったのかもしれません。
友だちができたので遊ぶお金がほしかったのか、バイトも始めるようになりました。遊びに夢中になりすぎて2年生のころから遅刻が増えだしましたが、3年生になり、さすがにマズいと思ったのか遅刻はしなくなりました。
通信制ですから遅刻や早退、欠席にしばられることはないんですが、バイトのこともあり、学校の遅刻は自分の問題で済むけれど、社会に出たときの遅刻は他人に迷惑をかけるんだよと、息子と真剣に話し合ったこともあります。
 アート部の打ち上げでたこ焼きパーティをやったときは、家からホットプレートを持っていき、けっこう盛り上がったようで、「楽しかった〜」と言って帰ってきたので、学校が本当に楽しいんだなと思ってうれしかったです。
アート部の打ち上げでたこ焼きパーティをやったときは、家からホットプレートを持っていき、けっこう盛り上がったようで、「楽しかった〜」と言って帰ってきたので、学校が本当に楽しいんだなと思ってうれしかったです。
|
不登校を経験して変わったこと
| 海野 |
不登校を通して、自分の中で変わったと思うことはありますか?
また、親子関係で変わったと思うことがあったら教えてください。
|
| B子 |
不登校で自分が嫌な思いをしたことで、他人への接し方が違ってきました。たとえば、何人かで話をしているときに、仲間はずれになっている子が出ないように声をかけるとか。
看護師を目指しているので意識して心がけていることもあり、そういう困っている人の存在に気づけるようになってきたのかなと思います。
先日、実習で受け持った患者さんが認知症で、「死にたい死にたい」といつも言っているんですが、「死にたい」という言葉の背後には、寂しいとか悲しいとか、人それぞれ違った感情があるということを教えてもらいました。
そのとき、不登校という自分の経験と重ね合わせて、その患者さんの立場になって考えて、患者さんの気持ちに少しは近づけたような気がして、自分のなかで成長できた部分かなと思ったりしました。
親子関係についても、以前からまわりに「仲がいいね」と言われることが多いのですが、不登校を通して自分の思っていることをすべて吐き出すことができたので、悩みごとなども隠さず言えるようになってきました。
|
| A男 |
人間関係で変わったのは、「ある程度、適当にやっていいんだ」と思えるようになったことです。学校に行けなくなった原因を自分なりに探ってみると、まわりの人たちと真面目に向き合いすぎたのかなと思います。
不登校になってから2〜3年かけて、「嫌だと思ったことは嫌だと言っても、相手はそんなに気にしない」とわかってきて、ある程度、人間関係は適当でも大丈夫なんだと思えるようになりました。
親子関係では、以前より自分が考えていることや感じていることを直接伝えるようになったと思います。
|
| 海野 |
現在、どんなことをしていますか? また、将来の夢があったら教えてください。最後に、会場の親御さんに向けてひと言、お願いします。
|
| A男 |
就職は医療機器メーカーを目指しています。いま医療の世界は技術や機器の進歩がめざましく、やりがいのある仕事かなと思っています。
会場の親御さんに何か申し上げるとしたら、血がつながっているとはいえ、親と子は別の人格をもった人間なので、互いの信頼関係はゼロに近いところから築いていかなければならないと感じています。
その信頼を、日々の小さなことから積み上げていかなければいけない。それは親だけでなく、子どもにとっても大事なことだと思います。
|
| B子 |
現在は看護師を目指して、日々看護学校で勉強をしています。精神的に傷ついた人を支えられる看護師になれるよう頑張りたいです。
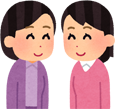 ここにいらっしゃる親御さんにお願いしたいのは、不登校の子どもはいつも不安な状態なので、「大丈夫だよ」と安心感を与えてあげて、焦らずゆっくり歩幅を合わせて一緒に歩いてあげてほしいと思います。
ここにいらっしゃる親御さんにお願いしたいのは、不登校の子どもはいつも不安な状態なので、「大丈夫だよ」と安心感を与えてあげて、焦らずゆっくり歩幅を合わせて一緒に歩いてあげてほしいと思います。
いま、この瞬間もお先真っ暗で、このまま進んでも無理なんじゃないかと思っている方もいると思いますが、絶対に何かのきっかけで思いがけない出来事と出会えると思うので、それを信じて前に進んでほしいと思います。
|
自分のモノサシで子どもを見ない
| 海野 |
ふたりのお母さん、お子さんの不登校を経験したことで、何か変わったと感じていることがあれば教えてください。
|
| B母 |
不登校を経験して変わったことは、子どもと価値観が違っても、まずは受け入れようと思うようになったことと、以前より娘の気持ちに寄り添えるようになったかなと思っています。
不登校中はネット仲間との交流も心配で、制限することも考えたんですが、あとで聞いたら、ネット上の友だちとの交流があったから変な方向に行かずに気持ちを保てたし、不登校をやり過ごすことができたと話してくれたので、いまではネットでのやりとりも肯定的にとらえられるようになりました。
そういう交流についても以前より話してくれるようになり、2人の間に垣根がなくなった気がするので、やっぱり不登校があってよかったのかな、と。
前の高校にいたら引っ込み思案のまま終わっていたかもしれないし、不登校になって転校することでダンス部と出会い、引っ込み思案の自分と真剣に向き合う機会を与えられたことは、本人も「一生分の運を使い果たした」と言うほど大きな意味があると思っています。
|
| A母 |
自分のモノサシで子どもを見ないようになったことと、子どもが考えていることをありのまま受け入れることができるようになった感じがします。
子どもを自分とは違うひとりの人間と思えるようになったし、子どもが不登校にならなければ、こうしたことには気づかなかったと思います。
不登校を通してかかわってくれた人たち、気にかけてくれた人たちとの出会いも、不登校になったからこそ得られたものなので、不登校で失ったものより得たもののほうが大きいと感じています。
 子どもはどんどん成長していくので、家で子どもと一緒に過ごす時間をもてたこと、その成長の節目節目に向き合うことができたことも、よかったなと思います。とても大切な時間だと思うので、それを親子で楽しめるようになればいいのかなと思っています。
子どもはどんどん成長していくので、家で子どもと一緒に過ごす時間をもてたこと、その成長の節目節目に向き合うことができたことも、よかったなと思います。とても大切な時間だと思うので、それを親子で楽しめるようになればいいのかなと思っています。
これからも実行していきたいのは、毎朝、子どもの顔を見て、笑顔で「おはよう」と言って一日をスタートさせたいということです。ありがとうございました。
|
| 海野 |
最後に、助言者の先生方からもひと言お願いします。
|
| 小栗 |
まず、A男さん、B子さん、おふたりとも高校を選ぶときのポイントが「楽しい学校生活を送れる」ことなのが共通していて印象的でした。それまで学校で嫌な思いをした経験があるからこそ、「高校で楽しい思い出をつくれるように」と思ったのかもしれません。
いま、社会はどんどん多様性を増し、子どもたちの多様性についてもさまざまに指摘されていますが、「学校」という場所はなかなか多様性を認めません。だから、自分と相性のよい学校と出会うことは非常に大事だし、不登校の子どもを受け入れてくれる居場所を探すことには大きな意味があると思います。
たとえばB子さんが、「授業には出ないのに、放課後の部活だけは参加するという日がかなりある」と言っていましたが、それを許してくれる高校はなかなかありません。でも、学校のどこかに、そういう「居場所」があることは非常に重要です。
ところで、今日のセミナーのテーマは「親子の葛藤を経て見えてきたもの」ですが、この「葛藤を経る」というのがすごく大事なんです。
子どもが不登校になると、親子の関係にさまざまな変化が起こります。その変化は、さざなみだったり暴風雨だったり、ご家庭によっていろいろですが、これまでの経験から言うと、葛藤が強くて激しいほど、その後の親子の関係性がすごく深まるような気がします。逆に、最初からあまり葛藤がなかったり、親の側が表面だけ子どもに合わせたり、変にものわかりのいい親をやっていたりすると、そこまで深い関係になれないんじゃないか。
親子の体験談を聴く意味は、「親と子の2つの視点で不登校という現象を見る」ということに尽きると思います。なぜ2つの視点で見ることが大事かというと、同じ現象でも見る人が異なれば、とらえ方も異なってくるからです。
親はよかれと思ってやったことでも、子どもはひどく傷ついていたり、逆に、親にとってはなんてことのないかかわりでも、子どもにとってはものすごく支えられた経験だったかもしれません。
今日のゲストのお話は、その「答え合わせ」のような意味合いもあるのかもしれません。
また、親子にとってはなんてことのないかかわりでも、私たち支援者から見ると素晴らしいかかわりだったりする可能性もあります。
さらに、その体験談を会場のみなさんの視点から見ていただくことで、新たな発見があるかもしれません。そういう視点をもって、今日の2組の親子のお話をとらえていただけるといいかなと思います。
|
| 荒井 |
B子さんとお母さんが学校見学に行ったとき、先生との面談の前に「この学校の雰囲気が嫌だったらネクタイを触って」というサインを決めていた話はとても興味深いですね。
お母さんの姿勢、つまり、本当の気持ちをストレートに伝えられないB子さんの性格を十分わかったうえで、お母さんが彼女の気持ちを第一にして学校を選ぼうとしている姿勢が伺えるエピソードだと思います。
この連携プレーは、親子の気持ちがひとつになったあらわれのようで、それを聞いた私たちまで幸せな気持ちにしてくれました。
不登校を経験した子と親は、知らず知らずのうちに不思議な力を身につけているような気がします。
これは昨年のセミナーで講師の方から教えていただいたことですが、いまのような先の見えない時代に必要な力は、「積極的に何かをする力」や「何かができる力」よりも、「何もできない状況を受けとめる力」「答えの出ない状況に耐える力」であると。
この力を「ネガティブ・ケイパビリティ」というそうですが、今日の2組のゲストの方々は、そうした力を身につけたのではないかと感じています。
|
| 海野 |
今日は2組のゲストに当時の経験をお話ししていただきました。
 いま、渦中にいるみなさんにとっては、「うちの子はこんなに立派じゃない」とか「そんなにうまくいくかなあ」とか複雑な思いもあるかと思いますが、現在、直面している状況が解決すれば、こんなふうに感じることができるんだという、ひとつの道しるべになったのではないかと思います。
いま、渦中にいるみなさんにとっては、「うちの子はこんなに立派じゃない」とか「そんなにうまくいくかなあ」とか複雑な思いもあるかと思いますが、現在、直面している状況が解決すれば、こんなふうに感じることができるんだという、ひとつの道しるべになったのではないかと思います。
ゲストのみなさん、長時間にわたりありがとうございました。また、会場のみなさん、ご静聴ありがとうございました。
|













 中学校では、最初の1カ月半くらいは頑張って通っていたんですが、何か嫌なことがあったらしく、ある日、家に帰ってくるなりカバンを玄関にほうりだして、「もう行かない!」と言ったんです。
中学校では、最初の1カ月半くらいは頑張って通っていたんですが、何か嫌なことがあったらしく、ある日、家に帰ってくるなりカバンを玄関にほうりだして、「もう行かない!」と言ったんです。 そのころは、毎日、「無理にでも行かなきゃダメだよ」と叱ったり、単位を落としそうになったときは「タクシーを呼ぶから、1時間でもいいから行ってきなさい」と無理やり行かせたりしました。
そのころは、毎日、「無理にでも行かなきゃダメだよ」と叱ったり、単位を落としそうになったときは「タクシーを呼ぶから、1時間でもいいから行ってきなさい」と無理やり行かせたりしました。 調理実習や校外学習は、すでに学校をやめるつもりでいたこともあり、事前にもらった案内で仲のいい子たちと一緒のグループだとわかったので、最後の思い出づくりのつもりで参加しました。
調理実習や校外学習は、すでに学校をやめるつもりでいたこともあり、事前にもらった案内で仲のいい子たちと一緒のグループだとわかったので、最後の思い出づくりのつもりで参加しました。 家庭内でのルールはとくに決めませんでしたが、ゲームの時間だけは2時間と制限しました。適応指導教室に行かない日はずっとやり続けることが多かったので、「これだけは守ろうね」と言いました。
家庭内でのルールはとくに決めませんでしたが、ゲームの時間だけは2時間と制限しました。適応指導教室に行かない日はずっとやり続けることが多かったので、「これだけは守ろうね」と言いました。 だから私にとって、そうした交流手段であるスマホを取り上げられることは親友を奪われることと同じだと思っていました。
だから私にとって、そうした交流手段であるスマホを取り上げられることは親友を奪われることと同じだと思っていました。
 もうひとつ、ランニングをするなかで感じたことがあります。
もうひとつ、ランニングをするなかで感じたことがあります。 そのころはまだ「学校に行くことがすべて」という考え方でしたが、しだいに最終目標は学校に行かせることではなく、「本人の自立」だと思うようになっていきました。
そのころはまだ「学校に行くことがすべて」という考え方でしたが、しだいに最終目標は学校に行かせることではなく、「本人の自立」だと思うようになっていきました。 看護師になりたいと母に伝えたのは、ペットや人の世話をするのが好きなのと、人の役に立ちたいという気持ちがあったからです。
看護師になりたいと母に伝えたのは、ペットや人の世話をするのが好きなのと、人の役に立ちたいという気持ちがあったからです。 親としては、小中学校のころのように学校が「嫌な場所」というイメージで終わるのではなく、楽しめる場所であってほしいと思っていました。
親としては、小中学校のころのように学校が「嫌な場所」というイメージで終わるのではなく、楽しめる場所であってほしいと思っていました。 そんな自分が1年間で成長できてオーディションも受けて、主役を演じることになるなんて自分でも信じられません。
そんな自分が1年間で成長できてオーディションも受けて、主役を演じることになるなんて自分でも信じられません。 アート部の打ち上げでたこ焼きパーティをやったときは、家からホットプレートを持っていき、けっこう盛り上がったようで、「楽しかった〜」と言って帰ってきたので、学校が本当に楽しいんだなと思ってうれしかったです。
アート部の打ち上げでたこ焼きパーティをやったときは、家からホットプレートを持っていき、けっこう盛り上がったようで、「楽しかった〜」と言って帰ってきたので、学校が本当に楽しいんだなと思ってうれしかったです。
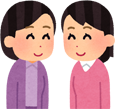 ここにいらっしゃる親御さんにお願いしたいのは、不登校の子どもはいつも不安な状態なので、「大丈夫だよ」と安心感を与えてあげて、焦らずゆっくり歩幅を合わせて一緒に歩いてあげてほしいと思います。
ここにいらっしゃる親御さんにお願いしたいのは、不登校の子どもはいつも不安な状態なので、「大丈夫だよ」と安心感を与えてあげて、焦らずゆっくり歩幅を合わせて一緒に歩いてあげてほしいと思います。 子どもはどんどん成長していくので、家で子どもと一緒に過ごす時間をもてたこと、その成長の節目節目に向き合うことができたことも、よかったなと思います。とても大切な時間だと思うので、それを親子で楽しめるようになればいいのかなと思っています。
子どもはどんどん成長していくので、家で子どもと一緒に過ごす時間をもてたこと、その成長の節目節目に向き合うことができたことも、よかったなと思います。とても大切な時間だと思うので、それを親子で楽しめるようになればいいのかなと思っています。 いま、渦中にいるみなさんにとっては、「うちの子はこんなに立派じゃない」とか「そんなにうまくいくかなあ」とか複雑な思いもあるかと思いますが、現在、直面している状況が解決すれば、こんなふうに感じることができるんだという、ひとつの道しるべになったのではないかと思います。
いま、渦中にいるみなさんにとっては、「うちの子はこんなに立派じゃない」とか「そんなにうまくいくかなあ」とか複雑な思いもあるかと思いますが、現在、直面している状況が解決すれば、こんなふうに感じることができるんだという、ひとつの道しるべになったのではないかと思います。